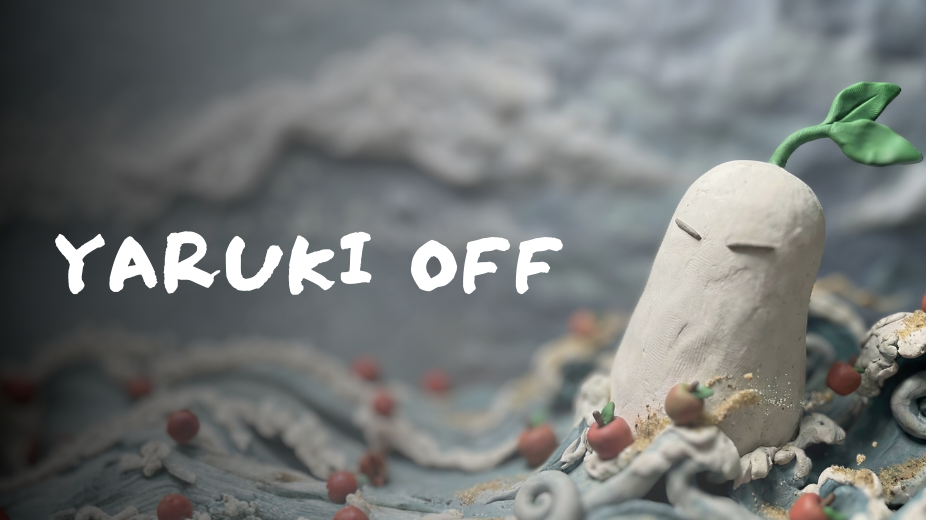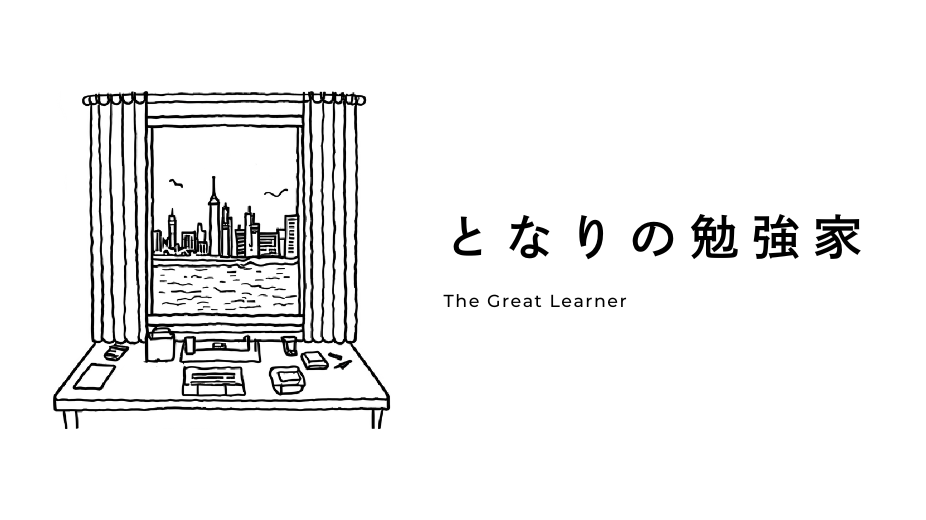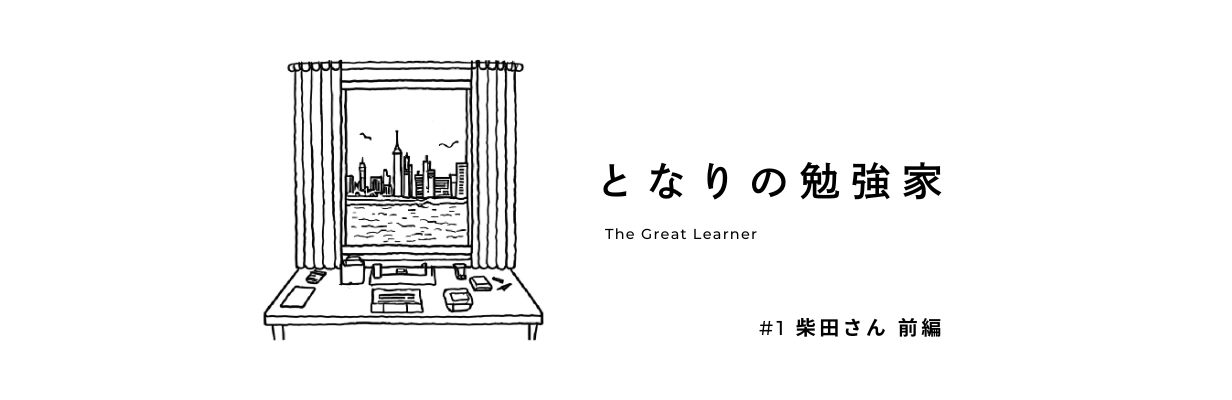
2025年8月27日
「資格の勉強は、基礎練だと思ってる」――元音大生・現エンジニア、柴田さんの“やる気の源”
となりの勉強家 #1 前編
「AWS認定資格を全12種取りました。」
「あとは、情報処理安全確保支援士。」
「今は中小企業診断士の勉強中です。」
……ちょっと待ってください、初手から情報量が多い。
この時点で「意識高い系の猛者かな?」と思った方もいるかもしれません。が、ご安心を。
今回ご紹介する柴田さんは、肩書きこそ立派ですが、話し方はほんわか、趣味はフルート、勉強の相棒はなまけもののぬいぐるみという、親しみやすさの塊のような“勉強家”です。
一見ストイック、中身は柔らかめ。そんな柴田さんの学びのスタイルを、今回はじっくりのぞいてみましょう。
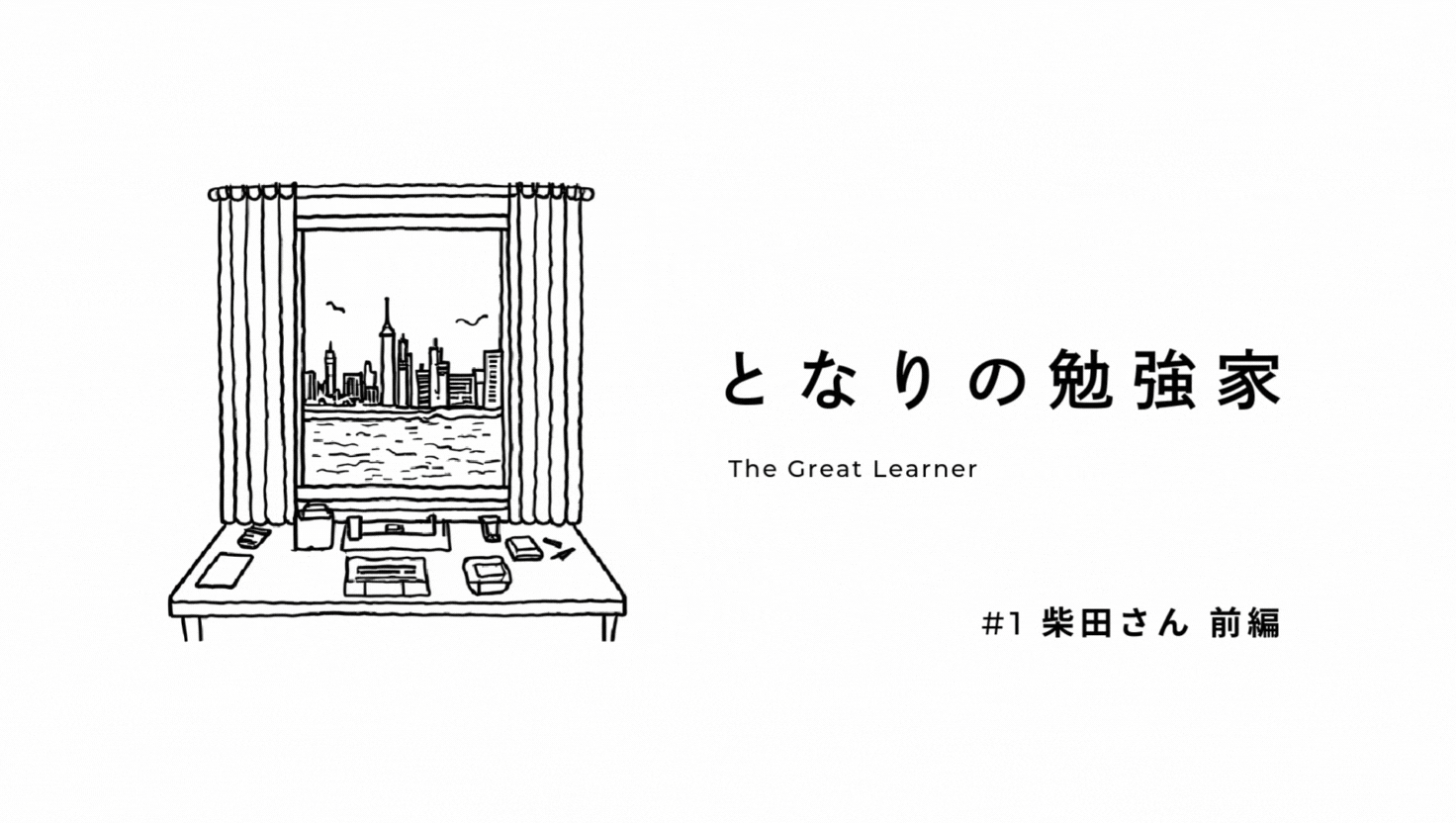
“フルートからエンジニアへ”――表現を届ける手段が変わっただけ
柴田さんはコクヨでシステムエンジニアとして働いています。現在は「@Tovas」というサービスの開発チームに所属し、日々サービスの開発に取り組みます。
そんな柴田さん、大学ではプロのフルート奏者を目指していた音大出身。かなり異色のキャリアの持ち主なんです。
「フルートが好きで、大学3年生までは本気で演奏家を目指していました。でも、コンクールやオーディションに挑戦するなかで、プロになる厳しさも実感して……。就活シーズンになって、改めて将来を考えたとき、自分は“演奏でお金を稼ぎたい”というより、“誰かに聴いてもらいたい”という気持ちのほうが強いと気付いたんです。」
そのとき、自分が音楽を通して本当にやりたかったことにも向き合ったといいます。
「CDを録る、演奏会を開く、自分の表現が人の記憶に残る……そんなふうに、誰かに何かを届けたいという気持ちが原動力だったんです。つまり“世の中に何かを残したい”という思いが、自分の中にずっとあったんだと、就活を通じて言語化できました。」
そうして出会ったのが、システムエンジニアという選択肢。 「自分がつくったものが社会に残る――ITの仕事にも、そんな側面があると知って、すごくしっくりきたんです。」
その後、転職を経て、今の職場であるコクヨに入社。前職ではシステムを受託開発する仕事をしていましたが、今は自社サービスを育てる立場にあります。
「売上に自分の頑張りが反映されるのが嬉しいですね。前の仕事はシステムを作ることがメインでしたが、今は“どう売るか”も含めて考えるので、視野が広がったと感じます。」

きっかけは仕事、モチベーションは“未来の自分”
柴田さんがこれまでに取り組んできた資格は、AWS認定資格全12種、情報処理安全確保支援士、そして中小企業診断士(これから受験予定)など多数。
「正直、最初から“この資格を取りたい!”と思っていたわけじゃなくて、仕事の中で必要に迫られて勉強を始めた感じです。AWSの資格は、クラウドの知識を体系的にキャッチアップしたくて。セキュリティの資格も、Webサービスの担当になって『もっとちゃんと知っておきたい』と思ったからでした。」
で、問題はここから。働きながら、どうやって勉強を続けるのか?
これ、多くの社会人にとっての超難問です。が、柴田さんはちょっと違うアプローチをとります。
「おすすめは、少しでもやる気が出たときに、受験日を決めて申し込んで、テキストを買って……逃げ道をふさぐこと(笑)。もうやるしかなくなります。」
意外とパワー系だ(笑)!確かに、お金を払ったら、やるか……となる部分はありますよね。
「あとは、僕の場合、“合格したあとの自分に憧れる”っていう気持ちも大きいです。社内で“セキュリティのことは任せて!”って言えるようになりたいとか、褒められたいっていう想いも原動力ですね。」
そしてもうひとつ、大きな支えになっているのが“チームの存在”なんだとか。
「会社のエンジニアチームのチャットに合格報告を流すと、みんなスタンプを連打してくれるんです。“神”“100点”“おめでとう!”って。一瞬で10個くらい来たりして(笑)。」
中でも“褒め神”と呼ばれる存在がいるとかいないとか……。
「めちゃくちゃ早くて複数のスタンプを押してくれる人がいて、あれが最高にやる気出るんですよね。」
“人は褒められると伸びる”の実例がここに。大人だって、褒められたい!

資格取得は“基礎練”。成果を出すための下地づくり
そんな柴田さんが資格勉強をどう捉えているかを聞くと、意外な答えが返ってきました。
「資格の勉強って、仕事やプライベートの“基礎練”だと思ってます。」
スポーツでも音楽でも、基礎ができていなければ応用は利きません。準備運動を怠ると、ケガをしてしまうように、基礎が抜けているとパフォーマンスにも影響が出る。仕事も同じだと柴田さんは言います。
「例えば小学生の頃、スポーツ少年団に入っていたような子って、どんな競技をやっても強かった記憶がないですか? サッカーでもマラソンでも、ドッジボールでも。日頃から“体の使い方”を訓練してるから、応用が利くんです。」
そして、仕事における“基礎練”にあたるものが、資格の勉強だと考えています。
「仕事って、正解がないことが多いですよね。“こんなの初めて”っていう状況も日常茶飯事。でも資格試験は、ちゃんと問題文を読めば、答えが一つに絞れるように作られている。その“正解がある世界”で、体系的に学び、問題を解く訓練をしておくと、仕事で“答えを見つけるセンス”が磨かれていくんです。」
勉強を通して身につけた思考力や判断力は、目に見えづらいけれど確かな武器になる。だからこそ、柴田さんは“資格=基礎練”という言葉を大事にしているのです。
難しいことをさらりと日常に落とし込んでしまう柴田さん。その姿勢が、“学び続ける”を自然体で実践しているように見える理由なのかもしれません。
……と、ここまでは“やる気の源”のお話。
後編ではいよいよ、柴田さんの「勉強の工夫」や「ゆるくて鋭い?マイルール」に迫ります。
なぜ試験に落ちたときに“ざまあみろ!”と言うのか? その真意とは――?
この記事でやる気オンしましたか?